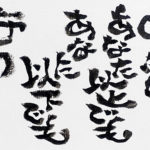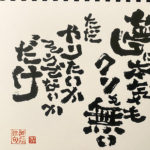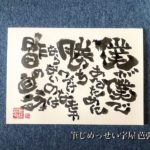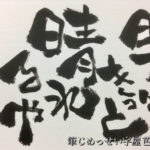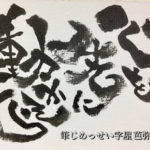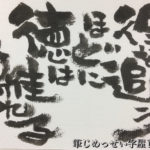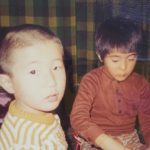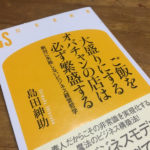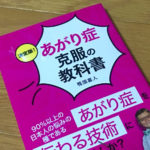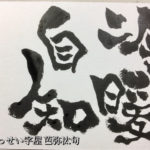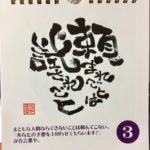2022/01/07
出雲大社をお詣りする際に、一緒にお詣りするといいと言われているところがいくつかあります。
その中でも、代表的なところが稲佐の浜。
神無月の神迎えの時、八百万の神々が出雲に集まる際に上陸してくるのが稲佐の浜です。
また、稲佐の浜を砂をすくって、出雲大社へ持っていき、出雲大社の本殿の裏側にある、「素鵞社(そがのやしろ)」 の裏手の床下の砂箱に奉納し、代わりに砂箱の砂を少しすくって持ち帰るとお守りになると言われています。
稲佐の浜は出雲大社から西に一キロほど。徒歩でも15分ほどで到着します。
砂浜にポツンと立っている弁天島が目印の美しい浜辺。
そこに沈む夕日が絶景のスポットになっており、日本のなぎさ100選にも選ばれています。
なぜ、浜辺にあるのに島というかというと、昔は砂浜が現在よりもっと手前で終わっていて、海の中の一つのしまだったそうです。
長い年月をへて砂が溜まり砂浜と一体化したようです。
さて、その稲佐の浜周辺は、古事記の神話の中でも大切なエピソードの一つである「国譲りの神話」の舞台となったと言われている場所です。
「国譲りの神話」とは、出雲地方を平定し国づくりを行っていた「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ) 」が、天照大御神の使いの「武甕槌神(たけみかづちのかみ)」 との話し合いにより、大きな争いをせず出雲地方を返上したという物語があります。
その働きを評価され、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ) は、天照大御神より巨大な出雲大社を与えられます。
「武甕槌神(たけみかづちのかみ)」 が大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)に対して、国の返上を求め、「否(いな)?然(さ)?」と聞いたことから稲佐の浜と呼ばれています。
ちなみにこの近くには、国の返上の話し合いの舞台となったと言われている「屏風岩」 という岩も存在しています。
ここ、稲佐の浜では旧暦の10月10日には、八百万の神々が集まると言われている神迎えの神事が行われています。
旧暦の10月を神無月というのに対して、出雲地方に神様が集まるということから出雲では神在月と言われています。
しかし、これは昔の人が漢字の意味からモジった後付け。大和の言葉は音の言霊で、漢字は音に合わせて付けたモノなので正しいとは言えないのです。
さて、話しは弁天島に戻ります。
この弁天島に祀られているのは岩上には豊玉毘古命(とよたまひこのみこと)を祀る小さな祠(ほこら)があります。
豊玉彦(よたまひこ) は日本書紀の上での名前であり、古事記上では大綿津見神(おおわたつみのかみ) とされています。
大綿津見神(おおわたつみのかみ) はイザナミ、イザナミの国生みの神話で生まれた神様で海をつかさどる神様。
瓊瓊杵尊(ににぎのみこと) の子供である山幸彦と海幸彦(やまさちひことうみさちひこ) の神話においては、「山幸彦」 と結婚する「豊玉姫命」 の父親として登場します。
「山幸彦」と「豊玉姫命(とよたまひめのみこと)」は、のちの日本建国を宣言する神武天皇の祖父母にあたりますので、大綿津見神(おおわたつみのかみ) は神武天皇の、ひいおじいさんということになります。
というように、この稲佐の浜には、日本の古典上の数々の物語を感じさせるところが沢山存在しています。
ぜひ、出雲大社に行く前に、稲佐の浜によって古事記の数々の神様の物語に想いを馳せてみるのはいかがでしょう。
それにしても、この日は天気良く、暑かったですが、稲佐の浜の美しさは素晴らしかったです。